皆さん、こんにちは!「下町AI探究者」のガジュマロです。
Googleさんの貴重な技術資料『Prompt Engineering』を道しるべに、AIへの「お願いの仕方(プロンプト)」を探求してきたこのシリーズも、今回でいよいよ最終回となりました。全6回、長きにわたりお付き合いいただき、本当にありがとうございます!
これまで、AIとの対話の基本から始まり、
- 第1回:AIの仕組みと「お願い上手」の基本
- 第2回:シンプルに頼む方法&お手本を見せる方法 (ゼロショット/フューショット)
- 第3回:AIに役割・ルール・状況を伝える工夫 (ロール/システム/コンテキスト)
- 第4回:AIにもっと深く考えてもらうヒント (ステップバック/CoT)
- 第5回:実践編!Excel作業などをAIに手伝ってもらうヒント
- 第6回:総集編!お願い上手・心得帖
といった内容を、皆さんと一緒に一歩ずつ探求してきました。
今回は、その総まとめとして、AIとこれから長く、賢く、そして楽しく付き合っていくための「お願い上手・心得帖」をお届けしたいと思います。これまでの学びをぎゅっと凝縮し、プロンプトを作る上で大切にしたいポイントをまとめました。
なぜ「お願いの仕方」が大切なのか?(最後にもう一度だけ!)
しつこいようですが(笑)、ここが一番のキモなので、最後にもう一度だけ。AIがどれだけ進化しても、その素晴らしい能力を最大限に引き出すための「鍵」を握っているのは、私たちユーザーの「お願いの仕方=プロンプト」です。
上手にお願いできれば…
- AIは私たちの意図をより正確に汲み取ってくれる
- 期待に近い、質の高い答えが返ってくる可能性が高まる
- 何度も聞き直したり、的外れな答えにがっかりしたりする時間が減る
- 結果的に、私たちの作業効率が上がったり、新しいアイデアが生まれたりする
つまり、プロンプトを工夫することは、AIという便利な道具をもっと上手に使いこなし、私たちの生活や仕事をより豊かにすることに繋がるんです。
お願い上手になるための「心得帖」~これだけは押さえたい7つのポイント~
では、具体的にどんなことを心がければ良いのでしょうか? これまでの探求とGoogleさんの資料のベストプラクティスを元に、特に大切だと感じたポイントを「7つの心得」としてまとめてみました。
心得1:とにかく「具体的に」伝えるべし!
- これが一番大事かもしれません。AIは長年連れ添った夫婦ではないので、「あれ」「それ」では伝わりません。「何を」「いつ」「どこで」「誰が」「なぜ」「どのように(5W1H)」を意識して、できるだけ具体的に、明確にお願いしましょう。
心得2:お手本(例)は最強の先生!
- 特に「こんな感じで答えてほしい」という形式やスタイルが決まっている時、あるいは微妙なニュアンスを伝えたい時は、言葉で説明するよりも、具体的でわかりやすいお手本(例)を1つか2つ見せてあげる(ワンショット/フューショット)のが非常に効果的です。AIも「なるほど、こうすればいいのね!」と理解しやすくなります。
心得3:「~してね」と、やってほしい事を伝えよう!
- 「〇〇しないでください」という禁止事項を並べるよりも、「代わりに〇〇してください」という肯定的な指示の方が、AIはスムーズに理解してくれることが多いようです。「ダメ」を伝えるより、「こうしてほしい」を具体的に伝えることを意識してみましょう。この辺、ちょっと人間の脳の仕組みに似ていて、面白いですね。
心得4:AIに「役割」を与えてみよう!
- AIに「あなたは〇〇の専門家です」「〇〇として答えてください」と役割(ロール)を与えるだけで、答えの質や口調、視点が変わって、欲しい答えが得られる可能性が高まります。また、一つの楽しみとして、「コメディアンの口調で」や「ラブコメの展開で」など、時には本筋と関係のない色々な役割を試してみると、AIの新たな一面が見えて面白いかもしれません。
心得5:答えの「出口(形式)」もイメージしよう!
- AIの答えは、必ずしも普通の文章である必要はありません。お願いする内容によっては、「箇条書きで」「表形式で」「JSON形式で」「コードで」のように、どんな形式で出力してほしいかを指定すると、後で情報を使ったり整理したりするのが格段に楽になります。
心得6:一度で諦めず、色々「試して」みよう!
- 最初から完璧なプロンプトを作るのは至難の業です。同じお願いでも、言葉遣いを少し変えたり、尋ねる順番を変えたり、形式を変えたりするだけで、AIの反応が変わることはよくあります。また、AI自身も日々進化しています。うまくいかなくてもがっかりせず、色々試してみる「試行錯誤」が大切です。
心得7:「上手くいったプロンプト」は記録しておこう!
- 試行錯誤の中で、「お、これは上手くいったぞ!」というプロンプトが見つかったら、ぜひメモに残しておきましょう! どんなAIで、どんな設定で、どんな言葉でお願いしたら、どんな良い結果が出たのか。自分だけの「成功プロンプト集」を作っておくと、後で似たようなお願いをしたい時に、絶対に役立ちます。記録は力なり、です!
AIとのお付き合いで、もう一つ大切なこと
この心得帖に加えて、AIと長く良い関係を築くために、心に留めておきたいことがあります。
- AIの限界を知ること: AIは残念ながら万能ではありません。間違えることもありますし、知らないこともあります。特に最新の情報や、倫理的に複雑な問題については注意が必要です。AIの答えを鵜呑みにせず、必ず自分で情報の真偽を確認したり、多角的に考えたりする姿勢を持ちましょう。
- セキュリティ意識: 個人情報や会社の機密情報など、外に晒すと問題になる情報は絶対に入れないようにしましょう。AIサービスを利用する際は、そのサービスのプライバシーポリシーなどを確認することも大切です。(詳しくは[過去記事:AIを使うと個人情報が心配?]も参考にしてください。)
- 楽しむ心!: これが一番大事かもしれません! AIは、私たちの仕事を助けてくれるだけでなく、新しい発見や学びを与えてくれる、知的なパートナーにもなり得ます。試行錯誤のプロセスも含めて、AIとの対話そのものを楽しむ気持ちを忘れずにいたいですね。
まとめ:AIと共に歩む未来へ
さて、全6回にわたってお届けしてきた「AIへのお願いの仕方」を探求するシリーズ、いかがでしたでしょうか。
プロンプトエンジニアリングというと難しく聞こえますが、要は「AIという新しい賢い道具と、どうすればうまくコミュニケーションをとれるか?」という、とても身近で大切なスキルなのだと思います。
今回ご紹介した「心得帖」が、皆さんのAIとの日々のお付き合いの中で、少しでもお役に立てば、これほど嬉しいことはありません。
AIは、私たちの未来をより豊かに、より便利にしてくれる可能性を秘めたテクノロジーです。怖がらず、かといって過信もせず、その特性を理解し、上手に付き合っていくことで、私たちの日常はもっとクリエイティブで、もっと楽しいものになると思います。
このブログ「下町AI探究者」も、これからも皆さんと一緒に、AIとの上手な付き合い方、そしてAIがもたらす未来について、楽しみながら探求していきたいと思っています。
最後までこのシリーズにお付き合いいただき、本当に、ありがとうございました!
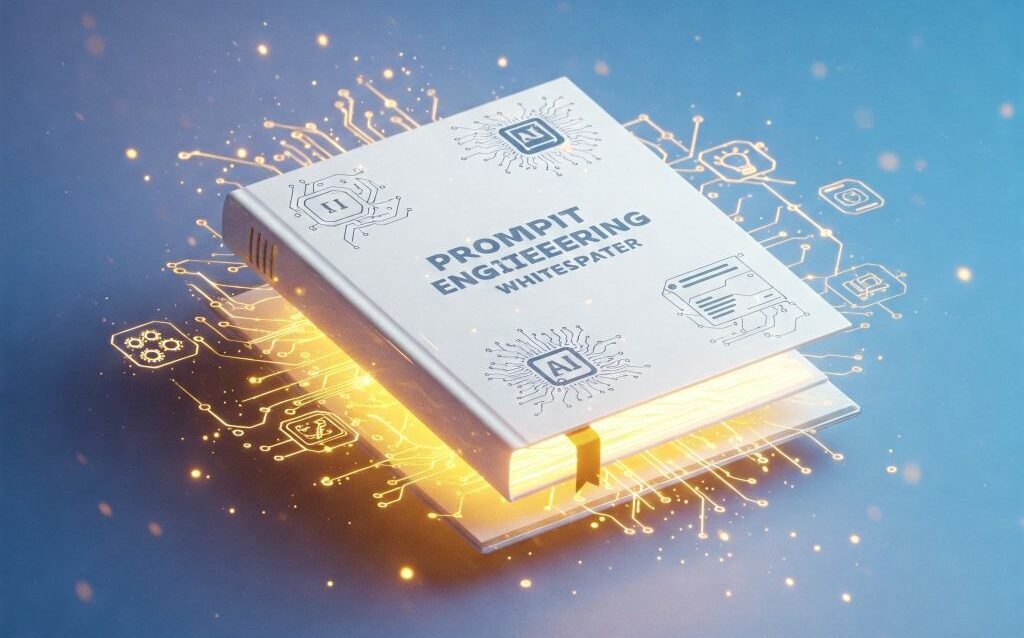


コメント